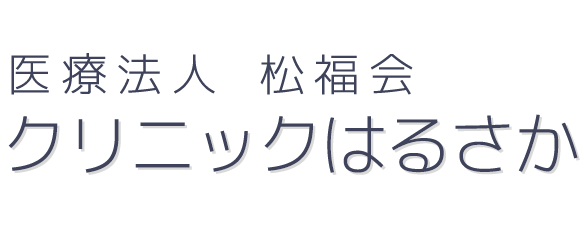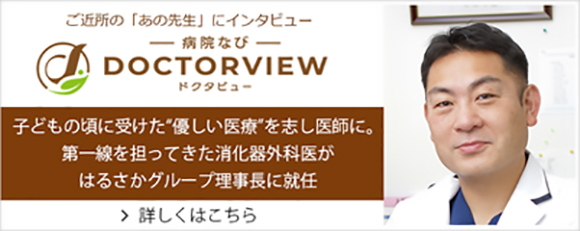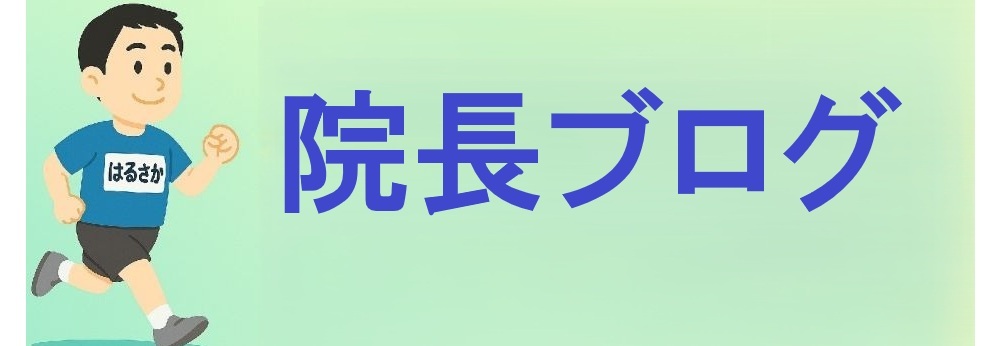おなかの症状(胃もたれ、食欲不振、胸やけ、便秘、など)
胃もたれ・食欲不振でお悩みの方へ
胃もたれや食欲不振は、日常生活でよくある症状のひとつですが、長く続くと生活の質を下げるだけでなく、消化器疾患のサインである可能性もあります。当院では、これらの症状に対し、専門的な視点から丁寧な診療と必要な検査を行い、原因を明らかにした上で適切な治療をご提案しています。
胃もたれ・食欲不振とは
- 胃もたれ:食後に胃が重たく感じたり、すっきりしない状態が続く症状です。
- 食欲不振:食事を摂る意欲が湧かず、食事量が減ってしまう状態を指します。
こうした症状は一時的な体調不良であることもありますが、慢性的に続く場合は、早めの対応が大切です。
主な原因
1. 機能性ディスペプシア(FD)
内視鏡で明らかな異常がないにもかかわらず、胃の不快感やもたれ、早期満腹感が続く状態です。ストレスや自律神経の乱れなどが関係しています。
2. 慢性胃炎・ピロリ菌感染
ヘリコバクター・ピロリ菌の感染によって胃粘膜に炎症が起こり、胃もたれや食欲低下の原因になることがあります。
3. 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃酸の影響で胃や十二指腸の粘膜が傷つき、痛みや胃の重だるさ、食欲不振を引き起こします。
4. 胃がん
初期には目立った症状が出にくく、食欲の低下や胃もたれが最初のサインになることもあります。中高年の方は特に注意が必要です。
5. ストレスや生活習慣の乱れ
不規則な食生活や睡眠不足、精神的ストレスは、自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きを低下させます。
当院での検査
症状の原因を明確にするため、以下の検査を行います。
- 胃内視鏡検査(胃カメラ) [胃カメラの詳細はこちら]
粘膜の状態を直接確認し、胃炎・潰瘍・ポリープ・がんなどの有無を調べます。 - ピロリ菌検査
呼気、血液、便などでピロリ菌感染の有無をチェックします。 - 血液検査
栄養状態や炎症の有無、貧血、肝機能・腎機能・甲状腺機能などを調べます。 - 腹部エコー(超音波)検査
肝臓、胆のう、膵臓など腹部臓器の異常がないかを確認します。
治療法
生活習慣の見直し
- 消化の良い食事を心がける
- 食べすぎ・早食いを避ける
- 睡眠や休養をしっかりとる
- ストレスをためこまない工夫をする
薬物療法
症状や検査結果に応じて、以下の薬剤を組み合わせて治療します。
- 胃酸分泌抑制薬
プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカーで、胃酸の過剰分泌を抑え、胃の負担を軽減します。 - 消化管運動促進薬
モサプリド、ドンペリドンなどが胃腸の動きを活発にし、もたれを改善します。 - 胃粘膜保護薬
レバミピドなどが胃の粘膜を修復・保護します。 - 抗不安薬・抗うつ薬
ストレスや自律神経の乱れが強く関与している場合、必要に応じて少量使用することもあります。 - 漢方薬
体質や症状に合わせて、六君子湯(ろっくんしとう)や半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)などを処方することがあります。胃腸の機能をやさしく整えたい方にも好評です。また食欲不振や胸やけなどの症状にも様々な漢方薬を患者さんの状態に応じて処方します。
ピロリ菌除菌療法
感染が確認された場合は、抗生物質と胃酸抑制薬を組み合わせた1週間の内服治療で除菌を行います。
受診の目安
次のような症状がある方は、早めの受診をおすすめします。
- 胃もたれや食欲不振が2週間以上続いている
- 体重の減少や疲れやすさを感じる
- 胃の不快感や痛みに加えて、吐き気や嘔吐がある
- 便に血が混じる、または黒い便が出る
胃の症状に、専門的な診療を
当院では、消化器内科・内視鏡の専門医が丁寧な問診と的確な検査を行い、患者様一人ひとりに合った治療を行っています。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。おなかの不調は、我慢せずに早めの対応が安心への第一歩です。
胸やけ・逆流性食道炎
胸やけ・逆流性食道炎でお困りの方へ
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、粘膜を刺激して炎症を起こす病気です。「胸が焼けるように熱い」「喉に酸っぱいものが上がってくる」「咳が続く」といった症状があり、日常生活の質を大きく低下させることもあります。
近年では、加齢、食生活の変化、ストレス、肥満などが要因となり、年代・性別を問わず増加傾向にあります。
主な症状
- 食後に胸やけやみぞおちの不快感を感じる
- 酸っぱい液体(胃酸)が喉に上がってくる感じがある(呑酸)
- 喉の違和感、声のかすれ、慢性的な咳
- 胸の奥のつかえる感じ、食欲低下
原因と悪化要因
逆流性食道炎の主な原因は、胃と食道の間にある「下部食道括約筋(LES)」の働きが弱くなることです。その結果、胃酸が逆流しやすくなり、食道粘膜が炎症を起こします。
悪化させる要因としては以下のようなものが挙げられます。
- 脂っこい食事、甘いもの、刺激物(香辛料・炭酸など)
- 食後すぐに横になる習慣
- 飲酒・喫煙
- 肥満・腹圧の上昇(妊娠・便秘など)
- ストレスや不規則な生活
診断方法
当院では、症状の確認に加えて必要に応じて以下の検査を行います。
- 問診・診察:症状や生活習慣を丁寧にお伺いします
- 胃内視鏡検査(経鼻または経口):食道の炎症やびらんの有無、胃の状態を直接観察します
- 血液検査・腹部超音波検査:他の消化器疾患の可能性を併せて確認します
治療について
1. 生活習慣の見直し
逆流性食道炎の症状軽減には、日常の工夫がとても効果的です。
- 食べすぎを避け、腹八分目を心がける
- 就寝の2~3時間前には食事を終える
- 高脂肪・高糖分・アルコール・カフェインの摂取を控える
- 適正体重を維持する(肥満改善)
- 禁煙、ストレス軽減を意識する
2. 薬物療法
症状の程度に応じて、以下の薬剤を組み合わせて使用します。
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):胃酸の分泌を強力に抑えます
- H2ブロッカー:胃酸を適度に抑える薬(軽症〜中等症に)
- 消化管運動促進薬:胃の動きを改善し、逆流を抑えます
- 粘膜保護薬:食道粘膜を守り、炎症を抑えます
当院の特徴
- 専門医による丁寧な内視鏡検査 [胃カメラの詳細はこちら]
- 日本消化器内視鏡学会の専門医が、鼻からの胃カメラや鎮静剤を用いた苦痛の少ない検査を行っています。
- わかりやすい説明と生活指導
検査結果や治療の進め方を丁寧にご説明し、食事・生活面のアドバイスも具体的にお伝えします。
胸やけ・逆流感でお悩みの方へ
「最近胸やけが続く」「薬を飲んでもよくならない」「市販薬で対応しているが不安」など、気になる症状があれば、ぜひ一度ご相談ください。早期に適切な対処をすることで、症状の改善や再発予防が可能になります。